お読みいただいている皆さんありがとうございます。プロリハ研究サロンの理学療法士、唐沢彰太です。(自己紹介はこちらから→唐沢彰太って誰?)
人は運動しながらいろいろなことを感じ、また感じるために動いて生きています。行為を行っていくためにはなくてはならないこのサイクルは、日々の生活でも実感できものです。
例えば、
- シャンプーがあとどれくらい残っているのかを確かめるためにボトルを持つ
- ベッドを買うときに、硬さを確かめるために座る
- タオルの手触りを確かめるために優しく触る
これらの時、「思っていた感じと違う!?」と驚いた経験を誰もがしたことがあるのではないでしょうか?
- シャンプーが思っていたより少なくて、軽かった
- ベッドのマットレスが思っていたより柔らかくて、座ると凄く沈んだ
- タオルの手触りが思っていたより硬く、手触りが悪かった
このような現象はどうして生じるのでしょうか?これを知っておくと、人の動きのメカニズムを知っていく上で大切な手掛かりとなります。
今回はこの「予測」について書いていきたいと思います。
視覚からいろいろなことを予測している
人には五感があります。視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚(体性感覚)の5つですが、人が行為を行う上で最も多くの情報量を脳に提供しているのが「視覚」です。<百聞は一見に如かず>という諺があるように、人の視覚に対する信頼度は非常に高いことがうかがえます。
では、人は行為において視覚からどんな情報を得ているのでしょうか?
いくつかの行為で考えて行きたいと思います。
上肢と視覚
1.コップを持つ
コップなどの物を持つ時には、視覚はどの様な情報を脳に提供しているのでしょうか?
- 物の同定:これから持つために見ている物が「コップ」だと認識するための情報
- 物の位置の同定:
コップがある場所がどこかを認識するための認識。自分から見て正面かどうか?机のどこにあるか?など様々な空間内で認識が必要 - コップの重さの予測:
今まで持ったことのあるコップなどから今から持つコップの重さを予測することで、どれくらいの力で持ち上げれば良いのかの手掛かりとする。 - コップの触覚の予測:
コップに触れたときの手触り、硬さ、温度などを予測して、コップを持った時の力加減や触れる面積などの手掛かりとする。
コップを持つ時の視覚の特徴としては、コップを認識して手を伸ばす方を決定するリーチングに関することと、コップを持つことに必要な<予測>をすることにあります。
2.鍵穴に鍵を入れる
- 鍵穴を認識する:コップの認識と同様
- 鍵穴の位置と向きを認識:コップの時の位置と同様
- カギを入れた時、また回したときの感覚の予測:
鍵穴に入っているか、また入れた鍵で合っているかなどの手掛かりに使用されます。
コップの時のような【持つ】動作がないため、何かを持った時の予測はありません。一方で、カギを回したときの感覚の予測がされています。
全身運動と視覚
3.段差昇降する
- 段差があることを認識する:
歩行から段差昇降をするための動作に変更する手掛かりに使われます。 - 段差の位置を認識する:
今の自分の位置からどれくらい先に段差があるのかを認識します。 - 段差の高さを認識する:
どれくらいの高さなのかを手掛かりに、足を上げる高さを予測します。
段差昇降の時の視覚は、段差に関する情報収集を中心に行われます。
安全にかつスムーズに段差をのぼるために必要な情報を視覚が脳に伝えてくれます。
4.外を歩く
- 周囲環境の情報収集:
車などの危険はないか、自分の進む方向はどっちかなど環境の把握を行います。 - 歩行速度・歩行の自覚:
周囲で流れていく景色と体性感覚と合わせて、自分がどれくらいの速さで歩いているのか、自分の足で今前に進んでいるといった自覚をします。 - 路面・床面の形状を認識する:
これから歩くところの形状の上を歩くとどんな感じがするのか、その感じに必要な姿勢の制御は何なのかを予測するために使用されます。
予測で動けるようになると動きはスムーズになる!
4つの行為で視覚の役割を見てきましたが、全ての行為で共通しているのが<予測>です。この予測は、今までの経験や記憶をもとにされるのが前提で、雪の上を歩いたことがない人と毎年歩いている人では、今から雪の上を歩くときにされる予測は全く異なるのは想像に難しくないと思います。
歩いたことがある人は、ほとんど普通の道を歩くように歩けますし、歩いたことがない人はひっぺり越しで全身に力を入れてへんてこりんな歩き方になります。
これは、雪を歩いた経験から、これから雪の上を歩く!という状況ですでに、踏みしめた感覚などを予測することが出来るからなのです。
この予測は、初めて行った動作の時は働きにくく、動作が習熟すればするほど出来るようになってきます。つまり、習熟した動作であればあるほど、予測のみで動けるくらい脳の負担は減っていきます。学習とのつながりが強いんです。いわゆるルーティーンに似たような感じかなと考えています。
人がいかに予測で生きているのか、反対に言えば予測が出来なければ人はスムーズに動く事すら出来ないのかがお分かりいただけたと思います。この予測がもし違うことに使われていたら…痛みがある人が動く前から痛みを予測したり…脳血管疾患の人が代償運動を予測していたら…。
介入に新しい視点を得られるきっかけになれば幸いです。
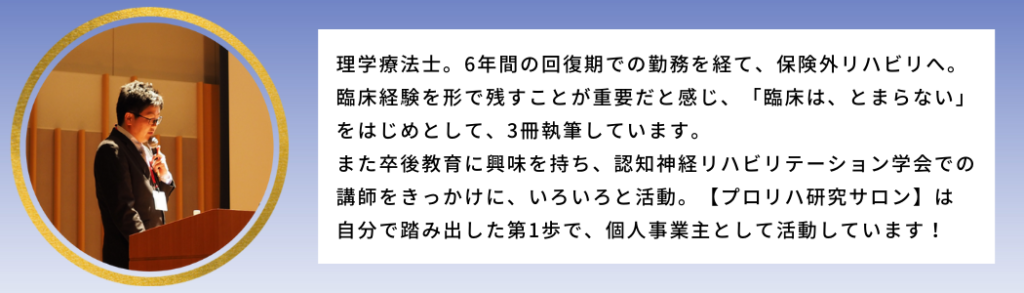
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
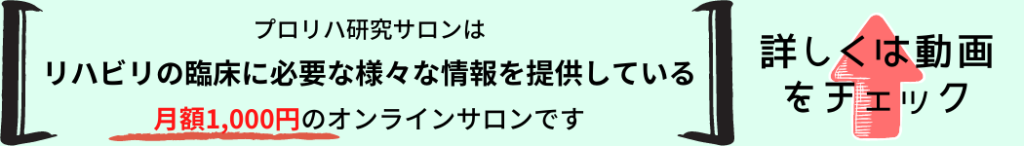
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
こちらもぜひご覧ください!!
〇過去の勉強会動画

