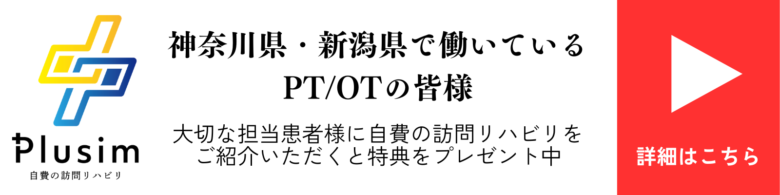お読みいただいている皆さんありがとうございます。
リハビリの臨床では、似ているけど意味が全く違う言葉がたくさんあります。【感覚と知覚】もそのうちの1つです。
この2つを使い分けることで、患者さんの病態の解釈がしやすくなったり、訓練のプログラムがより質の高いものになったりします。
そこで今回は、感覚と知覚の違いと、どう使い分けるのかを臨床に特化した方法でご紹介します!
是非こちらもご覧ください!
【運動・動作・行為を使い分ける!】
本ブログの内容はyoutubeでもご覧いただけます!
感覚と知覚
1.感覚
感覚という言葉自体はいろいろな意味を持っていますが、臨床上使いやすくするためには【感覚器に入力された刺激が脳に伝達されるまで】を指します。ここで重要なのは、感覚のレベルでは、まだ自覚できていないことです。
人は生きているだけで、無数の感覚が入力されています。これらすべてを自覚していては人はスムーズに動けなくなってしまうため、視覚床や脊髄でフィルタリングされています。自覚しなければならない感覚を選別しているんです。
今入力されている感覚を自覚するためには、注意を向けて知覚する必要があることになります。
この意味での感覚が障害されるのは、
1. 身体に存在する感覚器を損傷した時
2. 脳の頭頂葉にある感覚野を損傷した時
3. 脊髄を上行する神経線維を損傷した時
4. 並びに脳の中の感覚を伝達する神経線維や脳領域を損傷した時
になります。脳卒中や脊髄損傷、末梢神経障害などで感覚の障害が生じます。症状としては、痺れがみられたり、感覚が脱失したりします。
2.知覚
次に知覚です。
知覚と感覚の大きな違いは、刺激を自覚できるかどうかにあります。無数に入力されている感覚に注意を向け、自覚し刺激を知るプロセスが知覚になります。感覚よりも多くの機能が必要で、高次の機能と言えるかもしれません。
知覚の重要な点は人が知覚出来るのは1つまでということです。同時にいくつもの刺激を知覚することは基本的には出来ません。
例えば、椅子に座ってPCを操作している時、知覚しているのはPCの画面、つまり視覚になります。座っていることで感じている、臀部の座圧や足底の接触感などは意識すれば知覚出来る状態になっています。
ですが座圧や接触感に集中すると、PCの画面が見にくくなると思います。これが1つのことしか知覚出来ないということです。
では歩行中はどうでしょうか?
足が常に動いていますが、視覚からの情報収集に注力しています。この時の下肢の接触感覚や運動覚は知覚されているわけではなく、無意識で処理されています。
ここで重要なのは、いつでも注意を向ければ知覚できる状態である点です。脳卒中などで感覚障害が生じると、意識しても知覚出来ない状態になっていることがほとんどです。
つまり、すでに書いた感覚の障害ではなく、知覚の障害が生じているケースが圧倒的に多くなっています。
では、知覚にはどんな種類があるのでしょうか?接触を例に挙げていきます。
1. 刺激があるのか、無いのか
2. 身体のどこに刺激が入力されたのか
3. どれくらいの圧の刺激か
4. どれくらいの大きさの刺激なのか
5. どれくらいの長さ刺激が加わっているのか
6. どんな感じがするのか(硬い柔らかいなど)
この他にも摩擦や温度など様々な知覚があります。表在感覚を評価する時には、これらすべてを評価して患者さんが知覚出来るもの、出来ないものを整理していきます。
どうやって使い分けるのか
ここまでで感覚と知覚には、大きな違いがあることがお分かりいただけたと思います。実はこの知覚の先には【認知】があり、触れている物は何なのか?自分は今どういう姿勢なのか?などを知っていく段階があります。
これらを使い分けることで、患者さんの病態がより明確になり、必然的に訓練もより質の高いものを提供できるようになります。感覚と知覚をしっかりと分けて考える臨床、勉強しませんか?動画でも紹介しているので、合わせてごらんください!
プロリハ研究サロンでは、これらを使い分けて行う臨床を実例を踏まえて紹介しています。まずは公式LINEからお気軽にお問い合わせください!