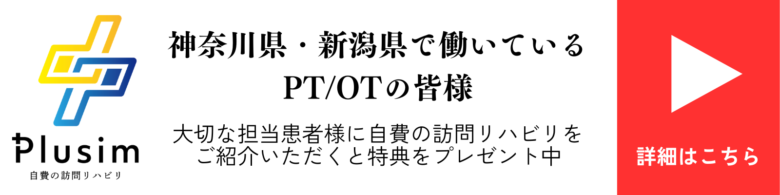お読みいただきありがとうございます。理学療法士の唐沢彰太です。
リハビリテーションの専門家として言葉を正しく理解して使用することはとても大切です。
臨床の中ではもちろん、多職種での連携が大切なリハビリではその面においても重要です。
その中でも「運動」「動作」「行為」の3つは似ている言葉ですが、実は意味が全然違う用語です。
そこで今回はこれら3つを意識的に使い分けると、頭を整理して臨床をスムーズに行えたり他職種の方への説明がしやすくなったりなど、いろいろなメリットをご紹介します。
非常に便利ですのでぜひご参考ください。
運動・動作・行為
はじめに、それぞれ3つの言葉に触れていきたいと思います。
今回の意味合いは、リハビリの臨床で頭を整理しやすくする目的でわかりやすくアレンジしています。
1,運動
<力が作用することで物体が動くこと>
運動は、関節を動かすことからランニングまで幅広く一般的に使用されています。
『運動しましょう』のような使われ方です。
ではリハビリではどういう使われ方がされているでしょうか?
動作や行為と使い分けるために『肘を曲げる』のような【同じ姿勢で行える動き】と解釈すると分かりやすいと思います。運動した結果、姿勢が変化しないで「座ったまま」「立ったまま」行えるものです。
リハビリではこの運動の獲得をゴールにはせず、病態解釈やプログラムを立てていくときに運動を使います。
観察・評価・分析をしていく中で「目標とする動作のどの運動に問題があるのか?」と言った具合です。具体的には立ち上がり動作の獲得を目標にした場合『膝関節の【運動】に問題がある』みたいな感じです。
運動は筋収縮を伴うことが基本ですが、他動運動など力源が他にある場合もあります。非常に幅広く使える便利な言葉ですが、同時に認識がズレやすい短所もありますので注意が必要です。
2,動作
<2つ以上の関節が協調して運動がすることで、姿勢の変化が生じること>
動作は運動とは異なり「姿勢が変化する」ものと解釈できます。
動作を行うと重心移動が生じ、同時に支持基底面(身体を支持する外部環境と接している面積)の変化が生じます。
<動き始めてから動き終わるまで>が動作であり【起き上がり動作】【立ち上がり動作】のように使います。
また行為との使い分けとして、動作には目的を含まないようにしています。
つまり「何のために起き上がったのか?」「起き上がって何をしたいのか?」のような目的は含まずに、身体の動きのみを動作としています。
こうすることで動作観察の時に、意図などの難しい要素を取り除いて身体の動きのみを考えることが出来ます。
よってリハビリでは、起き上がり動作の獲得を最終ゴールにしないで、<目的を達成するために起き上がれる(行為)>ことを最終目標にする考え方が大切になります。
3,行為
<意図があり、複数の運動や動作が組み合わさったもの>
行為は注意機能や認知機能などが意図に沿って、目的を達成するために働いています。
すでに書きました通りリハビリでは、この行為の獲得が目標となります。
「動作じゃないの?」と思うかもしれません。
ですがリハビリの時は起き上がれるのに、病棟では一人では起き上がれない患者さんをイメージすると「なるほど…」と納得すると思います。
もう少し詳しくこの問題の重要な点を2つ書いていきます。
- 病室とリハビリ室での環境の違い
例えば入院中病院では安定して歩けたのに、自宅では不安定になってしまった…こういう経験があるのではないでしょうか?
行為は、環境に適応して行わなければならりません。
その為、行為には【意図に沿った環境の情報収集と適応】が必要で、どの環境でもできる必要があります。 - リハ室と病棟生活や日常生活では、行為の意図と目的が違う
リハビリの時に行っているのは<動作練習やセラピストに言われたからやる>ことが目的であり、病棟生活や日常生活では<目的を達成することが目的>です。
もう少し具体的にするとリハビリの時は、動作を獲得するために動作練習をしていて、動作を行うことが目的になってきます。
立ち上がり練習で患者さんは、<トイレに行きたいから立ち上がる>といった意図を持って立ち上がるわけではありません。
一方生活では、<トイレに行くために立ち上がる>といった意図がある行為になります。
そうなるとリハ室で行っている動作練習では不十分で、自分の目的を達成するための行為の練習をする必要がなります。
つまり、リハビリ中にいかに意図を持ちこんで、病棟の時の<行為>を改善するのかが重要です。
どういう時に使い分ける?
では、実際にこの3つをどう使い分けるのでしょうか?
結論から言うと、病態仮説や目標を考える時と介入する時です。
つまり、患者さんの問題点と出来ている点を、それぞれ運動レベル、動作レベル、行為レベルでみていくことで、プログラムがはっきりするメリットがあります。
例えばこんな感じです。
- 関節運動自体に問題があるのか?(運動)
- それらを協調して動くことに問題があるのか?(動作)
- 高次脳機能障害などのえいきょうがあるのか?(行為)
こんな感じで病態解釈をクリアにすると、リハビリの目的が明確になります。
今行っているリハビリプログラムが、運動・動作・行為どのレベルが対象なのか整理できるのでスムーズにリハビリを行えます。
具体的には、
- どの姿勢でリハビリを行うのか
- 注意機能はどうか
- 意図や目的をイメージする必要はあるか
などを1つのプログラムにどこまで加えるかを考えやすくなり、行為の獲得までスムーズに向かえます。
また介入の結果、どの様な変化が生じたのかを細かく見ていく時にも役に立ちます。
いかがでしたでしょうか?
いつも何気なく使っている言葉かもしれませんが、すこし意識して使うだけで頭が整理されていくことを実感できると思います。
もっと具体的に臨床にどう生かしていけば良いのかを知りたい方は、まずはお気軽にご相談ください!