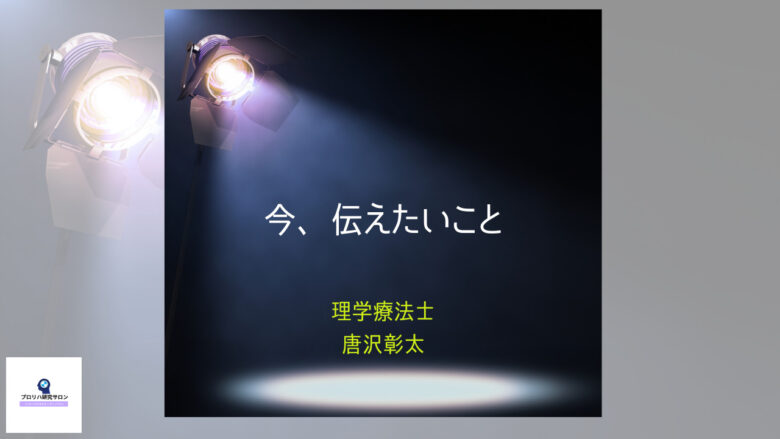お読みいただいている皆さんありがとうございます。
本サロンを運営しています、理学療法士の唐沢彰太です(自己紹介はこちらから→唐沢彰太って誰?)。
以前恩師からこんなことを聞かれたことがあります。
「唐沢君は何のために勉強しているの?」
勉強する理由を深く考えたことなかった私は、その場で咄嗟に、
「患者さんを改善するためです」
と答えました。
皆さんは何のために勉強していますか?
そんな勉強の方向性について私の考えを書いていきたいと思います。
必要なのは知識?それとも…?
解剖学、生理学、運動学、心理学、脳科学、神経学、リハビリテーション医学、装具学…。
リハビリテーションはたくさん勉強することがあり、いろいろな知識が必要です。
なぜこんなにも多くの知識が必要なのか?
それはリハビリが【人】を対象とした業種だからです。
近年では、理学療法士・作業療法士も専門性が求められ、認定療法士の制度も活発化してきています。
これは、理学療法士の学会が分科会で開催されていることからも分かるかと思います。
またこのような専門性の流れとは別に、エビデンスの重要性が高まってきています。
論文や学会発表など学術面での活動が今までよりも評価される時代に変ってきています。
さて、このように正しい知識を得ることが非常に重要な昨今ですが、病院などで勤務するPT/OTに必要なのは知識なのでしょうか?
もちろん知識は必要ですし、多いに越したことはありません。
冒頭で書いた質問の本質かもしれませんが、私が勉強するのは患者さんの為です。
脳や神経、人体の専門家になりたいわけではありませんし、なれるとも思っていません。
なので、知識を増やすために勉強しているわけではないですし、講義を行う為に知識を増やしているわけではありません。
私がPT/OTに必要なのは、勉強の前後だと思います。
つまり…
- どうして勉強しようと思ったのか?
- 勉強した内容をなにに還元しているのか?
私は、リハビリに行き詰まりにっちもさっちも行かなくなった経験があります。
その状況を打開するために勉強をしました。
同時に、同じような経験をしている後輩や仲間に少しでも役立てるようにアウトプットしています。
そして当然、私の学習の中心には患者さんがいます。
このサイクルが私を少しずつ成長させてくれたと思っています。
もちろん全員が成長を求めているわけではないのかもしれないですし、他の方法で成長している人もたくさんいると思います。
ですが、やはり担当した患者さんの今後の人生を左右する自責は持つべきだと思いますし、自分が担当で良かったと心から思ってもらえることが最大の喜びだと思っています。
いろいろな経験をして、自分だけの経験を1つでも持っているのであれば、伝えていくのが先輩の役目だと思っています。
誰が言ったのではなく、何を言ったのか
あの人が言っていた
あの人が言ってたことなんて…
この考えは私にとっては全く意味を持ちません。
実際臨床の中でも、後輩と話していてたくさんの気付きをもらっていますし、いろいろな方が講師の方の勉強会に参加し、多くのことを学んで来ています。
つまり、誰が言ったかよりも、何を言ったのかを大切にすれば成長できる場は比べ物にならないくらい増えるということです。
いつでも真剣に、尊敬の意を持って臨んでいきたいですね。
高次脳機能障害の観察のセミナー行います!!
ぜひご参加ください!!詳細はこちらから
⇨【高次脳機能障害を観察する!!】
スペシャルセミナー行います!!
来る7/30に、
「パーキンソン病患者に対するリハビリテーションの考え方」というテーマでセミナーを開催します!
興味をお持ちの方はぜひこちらご覧ください!
→第3回スペシャルセミナー
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
こちらもぜひご覧ください!!
〇オンラインサロンとは
〇過去の勉強会動画