お読みいただいている皆さんありがとうございます。プロリハ研究サロン、理学療法士の唐沢彰太です。(自己紹介はこちらから→唐沢彰太って誰?)
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)として働いていると分からないことばかり…勉強しないといけないのはわかっているけど何から手を付けたら良いのかわからない…そんな人多いと思います。
そんな人のために、これを勉強すれば役立つこと間違いなし!PT・OTなら知っていて損はない内容になっていますので、勉強に悩んでいる人はぜひご参考ください!
はじめに
リハビリテーション(以下、リハビリ)の臨床では、いろいろな疾患を担当するため、幅広い知識が必要とされます。そのため、多くのPTやOTの方から「何から勉強したら良いのか分かりません」と相談を受けてきました。
また、急性期・回復期・生活期など働く環境で必要な知識が違うため、勉強内容が変わってくるのもやっかいなところです。
よって、まずおススメなのが、【自分が担当している患者さんを、改善するために必要な勉強をする】ことなのですが…これでも幅広すぎて選べませんよね。
リハビリは疾患以前に<人>が対象で、<人>の理解を深めていくことが大切です。
その上で、今の職場や担当の患者さんに合った勉強をすることが大切です。
おススメ3選!
1.間違いない【運動学】
体の基礎といえば【解剖学】ですが、解剖学をそのまま臨床にいかすのって難しいんです…
そこで役立つのが、【運動学】です。
運動学は、筋の走行や関節の構造・動きなど、解剖学の大切な所を同時に学ぶことが出来ます。
また関節の動き方を理解することは、動作分析の能力をアップすることにもつながります。
動作を観察する時には、運動方向のベクトルが大切です。身体はどの方向に向かっているのか?重心はどの位置にあるのか?などを、矢印が浮かんでくるように見えるようになると、圧倒的に分析の質が上がります。
そのためには、人の運動を知ることが重要になるため、臨床に直結しやすい運動学が特におススメです。
今では運動学の本はたくさん出版されていてどれが良いか分かりにくいかも知れませんが、学生の頃授業で使っていた、イラストが多くて見やすいなど自分に合っている本が良いと思います。
ここでは2冊ご紹介します。
1冊目は【運動学で心が折れる前に読む本 松房 利憲(著)】です。先ほどのベクトルの部分などを非常にわかりやすく説明されていて初学者向けの本です。
2冊目は【身体運動学―関節の制御機構と筋機能― 市橋 則明(著)】です。こちらは運動学をより発展させた研究による知見を取り入れた本になっています。運動学をもっと詳しく知りたい人向けの本です。
2.これから必須の脳科学
体の動きを理解するのと同じくらい、これから必須となるのが、脳に関する知識です。
脳血管疾患だけではなく、運動器疾患においても、脳の知識は必須です。
脳に関する勉強も、体での解剖学、生理学、運動学みたいに、いろいろ種類があります。
脳の構造や機能から勉強すると、臨床にいかすのが難しい…そこで、脳全体の機能を勉強していくことをおススメします。
注意機能と脳機能、視覚と脳機能といったイメージです。
今回は、この脳機能がよくわかる本を2冊ご紹介します。
1冊目は【リハビリテーション臨床のための脳科学 〜運動麻痺治療のポイント 富永 孝紀(著) 他】です。リハビリのために書かれた脳科学に関する本で、臨床に繋げやすい書かれ方がしています。
2冊目は【高次脳機能の神経科学とニューロリハビリテーション 森岡周(著)】です。脳科学をリハビリの業界に広げた第1人者でもある森岡先生の著書です。脳科学というくくりから高次脳機能へと広げた最新の知見がたくさん入っている本です。PTOTが脳に興味を持ったらバイブルになる本です。
3.臨床の軸、心理学
臨床は、患者さんと1対1で行われます。
患者さんはどういう人なのか?今、何を考えて何をしようとしているのか?を理解することはとても重要です。痛みをもつ患者さんでは、情動面や心理面を理解しなければ、改善しない人はたくさんいます。脳卒中では、高次脳機能障害によって崩れた、認知面を理解しなければ、改善は難しいんです。
さらに、障害と向き合っている人は、どんな心理状態なのか?モチベーションはあるのか?が把握できなければ、リハビリを継続することすら難しいケースもあります。
そこで今回は、患者さんの心理面を理解するために、臨床でいかしやすく、研究もされている領域である【神経心理学】の本をご紹介します。
1冊目は【ジャクソンの神経心理学((神経心理学コレクション) 山鳥重(著)】です。神経心理学の父と呼ばれるジャクソンについて書かれた本になります。臨床の中で患者さんを良く観察することの大切さがわかる1冊です。
2冊目は【病理から見た神経心理学 (神経心理学コレクション) 石原 健司 (著)、塩田 純一 (著)】です。病態をもつ患者さんの心理がどう変化しているのかを考える知見を与えてくれる1冊です。
いかがでしょうか?どれも臨床の基盤となる知識を得ることが出来る本ばかりです。私が学生だった頃はこんなに本はなかったですが、反対にありすぎて悩んでしまうデメリットもありますよね。何から勉強したら良いか悩んだらぜひご参考ください。
プロリハ研究サロンでは1年目から10年目以上のセラピストが満足できる内容を、オンラインセミナーや記事などで学べます。
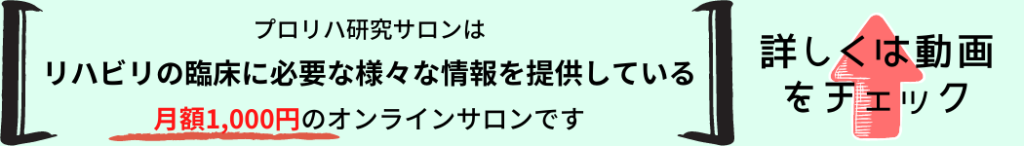
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
こちらもぜひご覧ください!!
〇過去の勉強会動画

.png)