お読みいただいている皆さんありがとうございます。プロリハ研究サロンの理学療法士、唐沢彰太です。(詳しくはこちら→唐沢彰太って誰?)
脳卒中後の後遺症の1つである【高次脳機能障害】には、皆さんからよくいただく質問あります。
それは、高次脳機能障害の検査は主に机上で行われるため、実際の動作や行為との関係性が理解しにくいことです。
例えば、机上検査では問題がなかったのに、病棟や自宅での生活場面になると注意障害の影響がみられるなどがあります。
反対に、机上検査では問題が見られたのに、日常生活場面では影響がみられない場合もあり、この時はリハビリとして介入する必要があるかどうかも考えなければなりません。
今回は、この高次脳機能障害の中でも特に観察から感知することや、実動作との関係が難しい【失行症】について書いていきます。
失行症って難しい…?
<失行症>って聞くと、皆さんどんなイメージでしょうか?
私が学校で習った失行症で記憶に残っているのは、手で狐を作ってマネしてもらう検査だけでした…。(お恥ずかしい)
セラピストとして働き始めてから、高次脳機能障害について勉強し始めましたが、失行症に関しては検査はもちろん、介入が難しくなかなか臨床に持ち込めずにいました。
これは皆さん同じなのではないでしょうか?
最近では、失行症に関する書籍や論文が急増している事もあり、私が新人だった頃よりも理解を深めやすい環境かもしれません。
ですが、いまだに介入は確立されておらず、検査と実行為、介入と実行為の距離はあまり縮まっていません。
これは以下の3つの原因があります。
- 机上での検査がメイン
- 簡易的に行える検査の「模倣」と実行為との関係の情報が著しく少ない
- 介入方法が明確ではなく、検査をしても臨床で訓練として実施しにくい
1は失行症に限らずですが、冒頭で書いた通り高次脳機能障害の検査が机上で行われることが多いため、実行為との差が生じることです。
この事については、近日中に別記事で書いていきますのでそちらをご参考ください。
2は、私が学校で習った記憶のある、狐をマネしてもらうなどの【模倣検査】についてになります。
この模倣検査は、失行症の検査で最も簡易的に行える検査で、私も臨床の中でスクリーニングとして使用することが多いです。
ですが、この模倣検査にも落とし穴があります。
それは、模倣が出来ない原因を考えなければ意味がないということです。
この模倣検査を行い、何かしらのエラーが見られた時、【どうしてそのエラーがみられたのか】の原因を考えます。
その原因が、実行為におけるエラーの原因と関係性があれば介入の対象になっていきます。
つまり、
- 模倣でのエラーの原因
- 実行為のエラーの原因
これらがわからないと意味がないということです。
失行症において、この点が最も難しく、重要な点になります。
2で書いたように、失行症は介入までの分析と考察が非常に重要になります。
加えて3の効果的な介入が未だに確立されていないことで、リハビリにおいて失行症はまだまだ難しい領域なのです。
見逃してませんか?失行症
そんな失行症ですが、一番の問題は半側空間無視などとは違い、観察から見つけることが困難な症状です。
言い換えると、検査を行わなければ【見逃してしまう】可能性が高いのです。
私が高次脳機能障害に関する勉強会で話をさせていただくときは、必ず「失行症の患者さんを担当したことがありますか?」と質問します。
すると、担当したことがある人は半分もおらず、ある勉強会では100人ほど参加者がいたにもかかわらず、10人も担当したことがないこともありました。
文献にもよりますが、失行症は左半球損傷の3~5割、失語症を呈している場合は7割もの罹患率です。
つまり、先ほどの勉強会のときの割合では数が少ないのです。
今お読みいただいている方も自分の担当患者さんを思い出してみてください。
もしかしたら、あの人失行症だったのかも…という患者さんがいるのではないでしょうか?
これらのことからも、失行症を検査をせずに見つけることは非常に困難であることは明らかです。
ですので、左半球損傷の方にはスクリーニングとして模倣検査を行うことをお勧めします。
もちろん、動作や行為の中で、失行症の徴候を見つけることも出来ますが、少し練習が必要です。
最初は全員にスクリーニングを行い、その方の動作や行為の特徴を覚えていってください。
すると、失行症の方の動作や行為の特徴が徐々に見えてきます。
ですが先述したように、模倣検査しただけでは意味がありません。
原因を考えて行くプロセス、その結果を実際の行為と結びつけるプロセス、最終的には介入までの一連の流れを知っている必要があります。
もしこの点について勉強していきたい方がいらっしゃればぜひオンラインサロンへご参加ください!!
一緒に勉強していきましょう!!
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
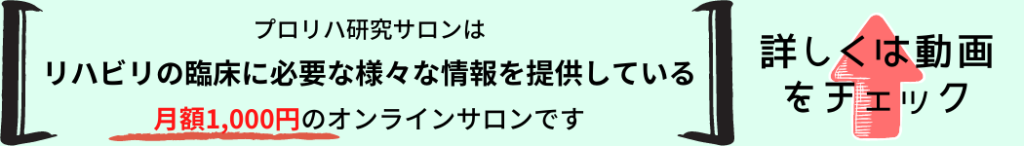
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
こちらもぜひご覧ください!!
〇過去の勉強会動画

