お読みいただいている皆さんありがとうございます。プロリハ研究サロンの理学療法士、唐沢彰太です。(自己紹介はこちらから→唐沢彰太って誰?)
理学療法士・作業療法士(セラピスト)の方と話していると、結構頻繁に【筋緊張】という言葉をよく聞きます。
皆さんもよく聞いたり、言ったりしていませんか?
そこで今回は、そんなよく使うけどあまりよく分からない筋緊張について、骨折後と脳卒中後で具体例を挙げながら、整理していきたいと思います。
そもそも筋緊張って?
例えば、私が以前いた回復期での臨床では、最初の20分~30分でリラクゼーションという名のマッサージやストレッチをほとんどのセラピストが行っていました。
入職して間もない私は当然疑問に思ったので聞いてみたところ…
「緊張が高くなっているから、正常化してから介入したほうが良い」と説明されました。
「でも、臥位でリラックスしても、起きたら戻らない…?」と思ったのを今でも覚えています。
実際皆さんも経験したことがあると思いますが、筋緊張というものは姿勢によって大きく変化します。
安静時筋緊張、動作時筋緊張という言葉があるように、止まってるときと動いたときの筋緊張は、違うんですよね。
もし動いている時に筋緊張が亢進するのであれば、筋緊張が亢進しない動き方を学習してもらう必要があります。
ところで、こんな筋緊張ですが次の現象と混乱しやすいです。
- 筋の柔軟性の低下(立位で前屈した時のハムストリングスや大腿二頭筋などのツッパリ感)
- 硬結(血流が悪くなったことによる現象)
- 持続的収縮による筋の膨隆
ここでは詳細は省きますが、臨床上これらと筋緊張は混乱しやすいです。そこで、整形外科疾患で生じやすい現象と、脳血管疾患で生じやすい現象に分けて、書いていきたいと思います。
骨折後の「硬さ」は筋緊張?
骨折の中でも、介入の頻度が高い疾患のうちの1つが大腿骨頸部骨折です。
頚部骨折後は、動作時痛がみられるため、股関節を動かしたくない状態になります。
すると、足を閉じた状態で寝ていたり起きたりするため、股関節内転筋群が持続的に収縮し、【硬さ】が生じます。
この硬さがなかなか改善しないんです。
セラピストが股関節を外転しようとすると、内転筋が伸張され痛みも生じる人もいます。
そこで大事なのが、この内転筋群の硬さが、筋緊張の亢進なのか?です。ストレッチやマッサージで【ほぐす】手法が、効果的かどうかも大切になります。
結論から言うと、このケースでは筋緊張異常よりも、防御性収縮と捉えた方が介入がスムーズになると思います。
股関節を動かすと痛みが生じるため、内転位で固定する無意識的な収縮です。
このケースで言えば、足を開いたりするといたいから、閉じた状態でキープしたい!と思い、常に力んでいる状態です。
そうなると、当然血流も悪くなりますし、筋の伸張性も低下(伸びにくくなる)してしまいます。
この状態では、ストレッチすると激痛がありますし、マッサージも一時的に血流の改善はしますが、また戻ってしまうことが多いです。
つまり、筋緊張の亢進ではなく、痛みを予測したことで生じる無意識的な収縮が、内転筋群の硬さの原因と考えた方が分かりやすいですね。
脳卒中後の関節の硬さは筋緊張?
脳出血・脳梗塞を発症すると、関節を他動的に動かした時に、抵抗感を感じる現象が頻発します。<ジャックナイフ現象>と呼ばれるものですね。
これは、伸張反射の異常亢進によるものと考えられていて、筋が急激に伸張された時に生じる伸張反射が敏感になっている状態です。
伸張反射は、速度依存的で、早く動かせば動かすほど抵抗感が強くなったり、関節運動を開始してすぐ抵抗を感じたりします。
神経系の異常であるため、筋緊張異常の一種として考えることも出来ますが、マッサージでは改善が難しく、効果が出ない場合がほとんどです。
また、脳卒中の発症初期では、ストレッチによって伸張反射の亢進を助長する可能性もあって、慎重に介入する必要があります。
脳卒中後の硬さは、脳損傷による神経系の問題による一次性の問題なのか、その状態が継続したことによる、二次性の生理学的な問題なのかを整理して、的確な介入をしたいところです。
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
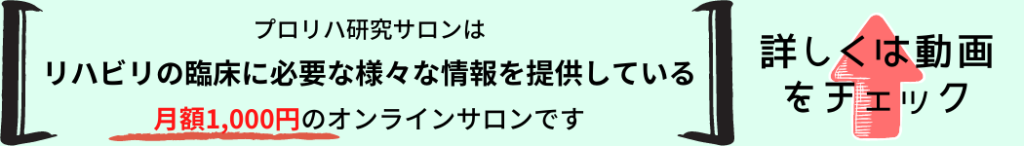
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
こちらもぜひご覧ください!!
〇過去の勉強会動画

