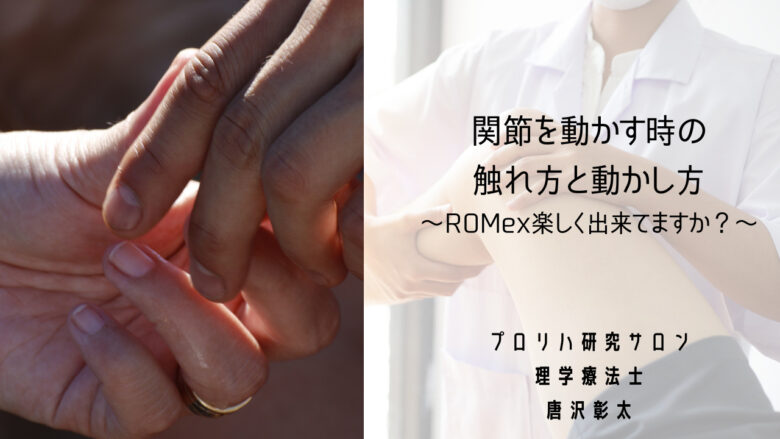お読みいただいている皆さんありがとうございます。
プロリハ研究サロンの理学療法士、唐沢彰太です。(自己紹介はこちらもご覧ください!→運営者情報)
病院や施設などの現場で働かれている皆さんは、関節可動域訓練(Range of motion exercise:以下ROMex)を行われていると思います。このROMexですが、実はものすごく技術が必要なこと知っていますか?
自分が計測した角度より、先輩が行った角度の方が10度も大きかったなどの経験をしたことがありませんか?
そんなROMexでとても大切になる、「触れ方」と「動かし方」について私が実践しているポイントについて紹介します。
その触れ方・動かし方で大丈夫??
人の体に200以上ある関節は、1つ1つ形や大きさが異なっています。それは体重を支える、細かな作業を行うなど目的が異なっていることが大きく影響しています。また、関節をまたいで走る筋も、関節の動きに大きな影響を与えています。
例えば、肩関節と股関節はどちらも球関節で、多軸に動ける特徴を持っていますが、股関節は荷重の役割を持っており、肩関節は大きな可動域を持っています。
これらを考えると、同じ関節の構造(球関節、蝶番関節、らせん関節など)をしていても、役割によって異なる関節の構成要素(腱板など)によって、1つ1つ特徴を持っています。また、筋の影響で各関節は、複雑な構造をしていることが分かります。このことを頭に入れて、患者さんの体に触れ・動かさなければ、関節を痛めたり、緊張が入ってしまったりと、ネガティブなことが起こります。
学生の頃、骨標本を見ながら学生同士で関節を動かした記憶があるのではないでしょうか。もっとも基本的なところは、動いている時の骨同士の位置関係です。そうです、滑りと転がりです。
どっちの骨が固定されて、どっちの骨が動いているのか?
その動きの中で、滑りと転がりは適切か?
これらを動かしながら考えなければいけません。
さらに、
筋の伸張性によって関節の軸がズレていないか?
抵抗を感じないか?
も考えなければなりません。そうなんです。
患者さんの体を「動かす」時には、同時に「感じる」必要があるのです。
動かすための触れ方と動かし方
感じるための触れ方と動かし方
これら2つは文字にすると似ていますが、実際にやられてみるとやられている側の感じ方が全く違います。皆さんは、何のために触れて動かしていますか?
1cm違うだけでこんなに変わる
関節の中でも、肩関節と股関節については動かし方が本当に難しいです。肩関節は肩甲骨、股関節は骨盤が関与しており、肩関節に至っては関与する関節が5つ以上あります。
こんな難しい関節ですが、少しポイントをおさえるとものすごく動かし方が上手くなります。
股関節では、背臥位で股関節を屈曲する時に、動き始めに骨盤が後傾し始める方がほとんどです。ですが、股関節の内外転、内外旋の角度をミリ単位で変化させて屈曲すると骨盤が後傾しないポジションがあります。ここのポジションから股関節を屈曲すると、たった1回の屈曲で股関節が見違えます。(文字にすると難しいですね(笑))
股関節にポイントがあるように、全関節にポイントが存在します。これらを知っていると、関節可動域訓練が楽しくてしようがないプログラムになります。
もちろんこの後学習を考慮した介入は必須ですが、まずは患者さんの心をつかむテクニックとして覚えてみてはいかがでしょうか?
プロリハ研究サロンでは、このような技術もお教えしています!!
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
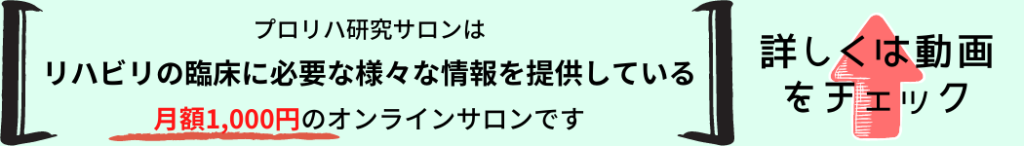
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
こちらもぜひご覧ください!!
〇過去の勉強会動画