お読みいただいている皆さんありがとうございます。プロリハ研究サロンの理学療法士、唐沢彰太です。(自己紹介はこちらから→唐沢彰太って誰?)
患者さんの動作を改善することを目標とするリハビリテーションでは、患者さんが今どう動いているのか?を分析することはとても大切です。
ですが、私が今まで出会った理学療法士や作業療法士(PT/OT)の方々には、この動作を分析することが苦手な人が多かったんです。
その人たちの話を聞いていく中で、いくつか共通点があったことに気付きました。
今回は、その共通点と解決策を書いていきたいと思います!!
動作分析ってなにすれば良いの?
私が学生だった頃、臨床実習で担当させていただいた症例の方の基本動作(寝返り、起き上がり、立ち上がり)と歩行の分析をレポートに書いている時でした。
「動作観察と動作分析があって、動作分析では何を書いたら良いんだろう…」
そうなんです。
結局何を書いたら良いのか分からないんです。
観察との違いも微妙ですし、評価結果をどう分析にいかしたらよいのかもわからない。
しかも、実際に臨床現場に出ると、学生の頃すべてを網羅するように行っていた評価も「トップダウン」という名目で行わなくなってますますわからない…。
こういった経緯があって、動作分析が苦手になっていく人がたくさんいます。
仕方がないことなんですね。
では、動作分析は何をすれば良いのか?
それは…
【仮説を立てる!!】
これに尽きます。
リハビリの臨床現場では、まず動作観察と動作分析から行われます。
(観察と分析の違いはサロン内で話しているので興味のある方は是非1度入会してみてください!)
これら観察と分析から得られた情報を元に、評価と介入プログラムを考えて行く流れになります。
つまり、動作観察と分析で【何をみるのか】、さらに【何を考えるのか】によって評価と介入が左右されてくるということです。
具体的にどんな仮説を立てていくのか考えて行きます。
仮説を立てて検証し【知恵】にしていく
動作観察と動作分析それぞれどんなことをみて考えて行けば良いのか?
- 動作観察
【どんな特徴のあるうごきなのか?】 - 動作分析
【どうしてこんな特徴の動き方なのか?】
となります。
まず観察で全体像をつかみ、分析でその原因を考えて行く流れです。
ですが、ここで気を付けなければならないのは、
<動作分析で考えた原因はまだ仮説でしかない>
ということです。
例えば、大腿骨頸部骨折の患者さんが骨折側に荷重しないように立ち上がっている時、<痛みが原因>だと考えたとします。
ですが、これはまだ確証はなく仮説でしかありません。
この動作分析から考えた仮説を元に、評価を実施していく形になります。
例えば、痛みの検査、立位での骨折側への荷重のやり方の分析と痛みの度合いなどをみていきます。
これらの結果から、分析で立てた仮説の<痛みが原因>が確からしいかどうかを更に考え、プログラムを考えます。
このように、分析で考えた原因は仮説なんだ!ということを念頭に置いて評価を進めていくことが大切です。
まとめます。
動作分析では、答えを出す必要はありません。
自分なりの考え=仮説を持って評価・仮説に進んでいくプロセスの1つが動作分析です。
この仮説→検証を繰り返していくことで、経験を積み重ねて<知恵>として貯めていくことが大切です。
動作分析が苦手なあなた。
答えを出そうとしていませんか?
焦らず丁寧に組み立てていくことを大切にしてみてください。
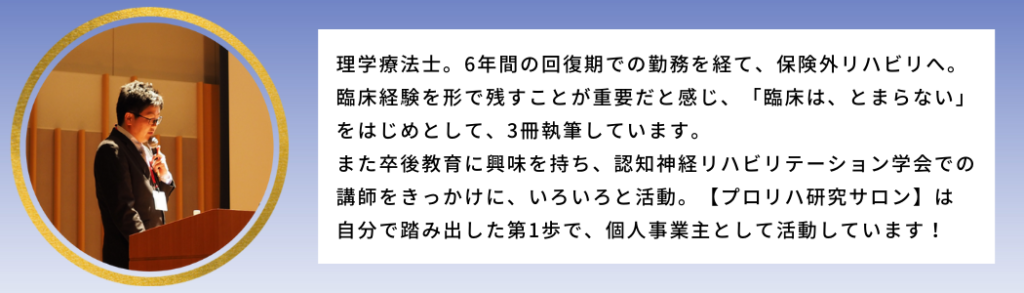
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
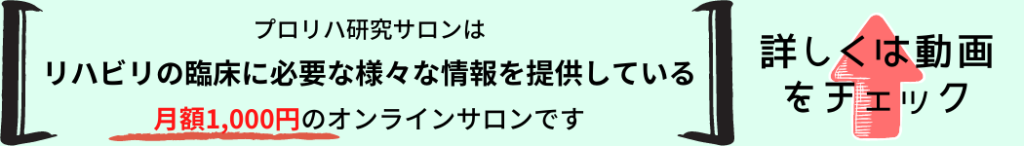
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
こちらもぜひご覧ください!!
〇過去の勉強会動画

