お読みいただいている皆さんありがとうございます。
本サロンを運営しています、理学療法士の唐沢彰太です(自己紹介はこちらから→唐沢彰太って誰?)。
<注意障害>は臨床現場では毎日のように聞く言葉です。実際、脳血管疾患の患者さんでは非常に高い割合で注意に関する能力が低下しています。ですが、この注意障害に頻繁にあうこと、病態が一見単純に見えることから安易に「患者さん注意障害あるよね」と言ってしまいがちです。
そこで今回は、注意障害を整理しながら、知覚との関係や行為との関係を書いていきたいと思います。
注意障害の本当に大切なことは…
注意はいろいろな分類がなされています。その中でも最も有名なのが、
- 持続性:注意を喚起した状態を保つ能力
- 分配性:2つ以上の物事へ注意を払う能力
- 転換性(転導):注意の対象を変えるなどの変化させる能力
- 選択性:注意する対象を意図に応じて選択する能力
です。この分類が浸透したことによって、臨床では患者さんがどの注意能力の低下が生じていることを判断することが第1段階とすることが多いです。もちろん検査を実施した上で判断することはとても大切ですが、その前に1つ考えなければならないことがあります。
それは…
【注意ってそもそもどんな役割を持っているの?】
例えば、起き上がる時に注意はどういった役割を持っているのか?歩行の時はどうか、上肢での道具使用の時はどうか…。
これらを考えなければ、注意障害とリハビリによる介入は大きな距離を持ってしまいます。これらのことから、患者さんを観察していく上で、
- 注意障害が行為や動作にどう影響しているのか?
- それは改善出来る可能性があるのか?
- 介入の対象になりうるのか?
これらを考えていくことが、注意障害において大切なことになります。
行為では注意はこんな役割がある!の例
そこで、少し例を出して考えて行きたいと思います。
①注意は知覚するためには必須の能力であること
触れている、動いているなどの知覚は注意によって引き起こされます。
例えば、掌がベッドに触れていることを知覚するためには、掌に注意を向けた上で掌を意識しなければなりません。
起き上がる時に、ベッドに掌が触れ、圧が加わっていることが知覚されると、自分がどれくらい掌に体重を乗せているのかを認知することが出来ます。
もし、掌に注意を向けることが出来なければ、掌を意識することも、触れていることを知覚することも、どれくらい体重が乗っているのかを認知することも出来ません。
こういった状態で、掌をベッドに付けてスムーズに起き上がることが難しいのは想像に難しくありません。もしかしたら手をベッドにつかないように起き上がるかもしれません。
このように、自分の身体に注意を向けることが出来ない場合は、知覚が上手く行えない可能性が考えられるため、動作や行為に大きな影響を及ぼします。
②行為を行う時に注意する場所は介入の時とは違うことが多い
リハビリの介入では、セラピストが患者さんに注意して欲しい所があります。
その箇所へ注意を向けてもらうために、声掛けや感覚刺激を入力することは珍しくありません。
ですが、その注意して欲しい場所は実際に行為を行うときに注意する場所とは異なることが多いんです。
その代表例が歩行訓練でしょう。介入では、足底や関節覚など自分の身体に注意を向けるような指示をすることが多いですが、実際の歩行では視覚性の注意を中心に使用しているため大きな差が生まれます。よって、膝に注意を向けていれば上手く歩けるけど病棟ではうまく出来ないといった、難題にぶつかってしまうということです。
この時に気を付けなければならないのは、患者さんが自然歩行の時に何に注意を向けているのかを知ることです。もしそこに、注意障害が影響しているのであれば、そこを考慮して介入を進めていく必要があります。
このように、行為と注意、注意と介入、介入と行為はそれぞれの関係性を考えて観察し評価をし、介入していく必要があるということですね。みなさんは目で見える動作や運動だけではなく、目に見えない注意をどう考えていますか?
実は動作から注意を観察することも出来るんです!
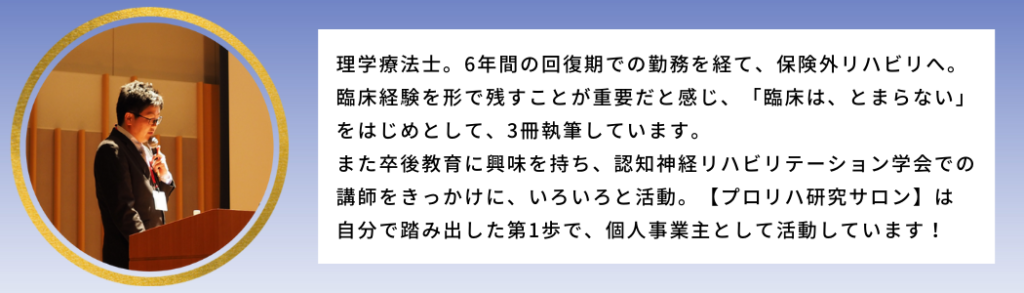
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
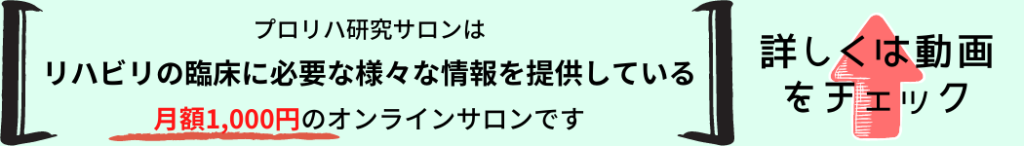
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
こちらもぜひご覧ください!!
〇過去の勉強会動画

