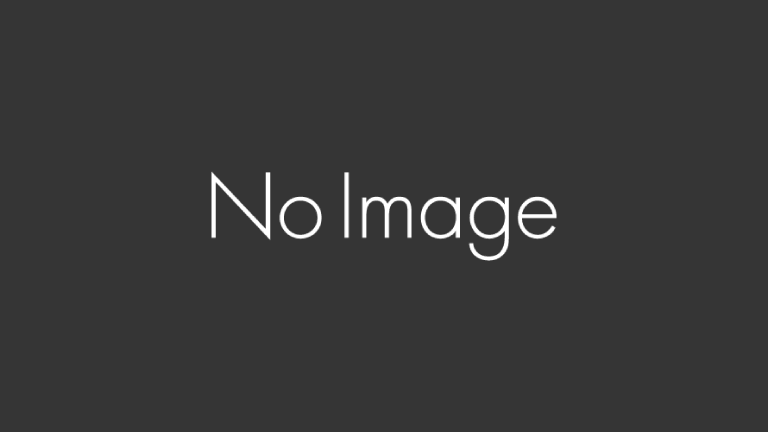お読みいただいている皆さんありがとうございます。プロリハ研究サロンを運営しております、理学療法士の唐沢彰太です(自己紹介はこちら→運営者紹介)。
臨床で姿勢や動作を観察することは、患者さんが獲得したい動作や行為に介入するためには非常に大切です。でも、観察結果をどうやって活かせば良いのかって難しくないですか?
実は、観察にはやり方があって、正しくやらないと【ただみるだけ】になってしまうので注意が必要です。
そこで、簡単にできる観察のやり方を紹介していきます。
観察ってそもそも何のためにやるの?
学生の頃に行った臨床実習で、姿勢観察・動作分析を行いレポートに書いたことは皆さんあると思います。姿勢観察や動作観察の目的は、「患者さんの身体がどうなっているか?」を言語化することにあります。
例えば、座位姿勢を観察した時には、頭からつま先までの向きや角度を事細かに記載していき、その人の座位を見たことがない人でもイメージが出来るような情報にしていきます。ですが、実際の臨床でここまで事細かに記載する必要があるのかと言うと…ですが、「観察の技術を学ぶ」意味では、まず全身の状態を書けるようになることは大切です。
では、実際の臨床での観察は何をすれば良いのでしょうか?良く耳にするのは、「正常との違いを見つける」ですが、これはあまりおススメしません。リハビリは、その人らしい生活を再獲得することにあり、正常な生活のような一般化されたものを獲得することが目的ではありません。特に障害にも個人差があるため、今の身体に合った動作を獲得するためには、今の動きをしっかりと観察する必要があります。つまり、【今よりも楽に動ける・姿勢を保持できるようになるためにはどうすれば良いのか?】を考えていく上で、観察で得た情報を活かすことが大切です。
このことを踏まえると、観察では【正常との差】ではなく【左右差】を見ていくことが最優先になります。では具体的にどうやっていくのか?…気になる方は動画にまとめたので是非見てみてください!
プロリハ研究サロンでは、
・実際にどうやって評価していくのか?
・その評価結果をどうやって介入にいかしていくのか?
臨床に直結する形で学べます!
こちらもぜひご覧ください!!
〇過去の勉強会動画