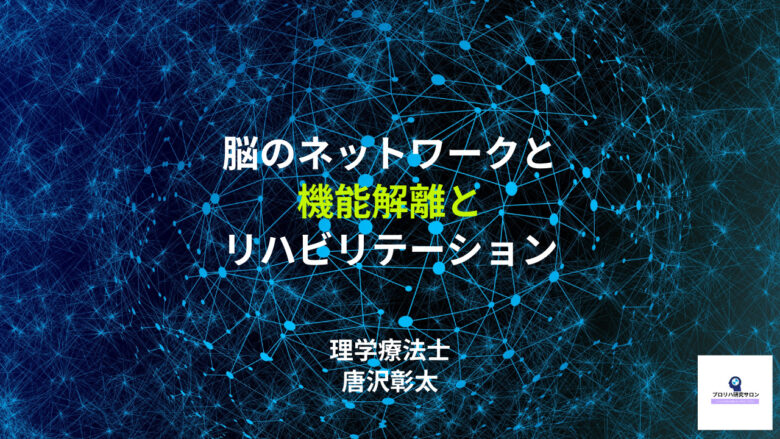お読みいただいている皆さんありがとうございます。
本サロンを運営しています、理学療法士の唐沢彰太です。
(自己紹介はこちらから→唐沢彰太って誰?)
視床出血や被殻出血、中大脳動脈梗塞など脳血管疾患では損傷する部位が特定されます。
基本的には損傷した部位が担う機能が障害を受けますが、実は損傷を受けていない部位の機能も障害を受けているのをご存知ですか?
今回は脳血管疾患において重要な知見である、機能解離(機能抑制)-diaschisis-について書いていきたいと思います。
機能解離という脳の不思議
そもそも機能解離(diaschisis)とは何なのでしょうか?
これを理解していくために、脳の不思議について知っておく必要があります。
脳には機能局在が存在しています。
前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉に分けられる新皮質に加え、視床、基底核、小脳など様々な部位から脳は構成されています。
この部位別に役割があり、脳損傷ではその損傷した部位の役割が障害を受けるというのが一般的な考え方なのは最初に書いた通りです。
この部位別の役割に加え、脳には別の視点が必要です。
脳は、神経で構成されていてその状態は網目のようにネットワークを構成しています。
つまり、部位内で情報をやり取りしているのはもちろん、部位同士で情報のやり取りをしています。
頭頂葉で処理された情報は前頭葉へと伝達されるといった具合です。
このようなやり取りがありとあらゆるところで行われている脳は、部位別だけで考えるのは到底不可能で、ネットワーク別に捉えていく必要も出てきます。
ネットワークとして脳を捉えていくと、機能解離は理解しやすくなっていきます。
例えば、ABCでネットワークが作られているとします。
脳出血などでAが損傷すると、Aの持つ役割はもちろん障害を受けます。
同時に、ABCのネットワークも働かなくなり、BとCも一時的に機能を停止してしまいます。
これは、Aが機能停止しているのにBとCが活動してしまうと、Aの損傷度合いが更に重症化する恐れがあるからです。
仕組み的には、脊髄ショックのようなものと考えると分かりやすいかもしれません。
この機能解離は、1914年にMonakowによって提唱され、近年ではその詳細がほぼ解明されてきています。
患者さんをみることの重要性
このように、損傷部位以外の障害が実際に生じていることを考えると、脳画像の活用方法や部位別の症状などの臨床における使い方が大きく変化してきます。
あくまで情報の1つとして使用していかなければ、患者さんの重要な点を見逃してしまう可能性があるからです。
そうなってくると、臨床の中で患者さんを観察することの重要性が非常に高くなってきます。
患者さんの振る舞いや言動、更に検査結果や評価結果などから患者さんの特徴を把握していくプロセスがリハビリでは必須です。
この時、○○損傷だから…とバイアスをかけずに、機能解離という知見をもとに損傷部位以外の障害も視野に入れて進めていくことが大切です。
小脳の損傷によって前頭葉の機能が低下することしかり、前頭葉の損傷によって頭頂葉の機能が低下することしかり様々なつながりが脳にはあります。
臨床にこのつながりを取り込んで、広い視野で介入していきたいと思います。
感覚障害に関するセミナー行います!!
まだ先ですが、8/31に、
「感覚障害」をテーマにセミナーを開催します!
主に脳卒中後の感覚障害についての内容になります。
興味をお持ちの方はぜひこちらご覧ください!
→第2回オンラインセミナー「感覚障害の評価と介入」
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
こちらもぜひご覧ください!!
〇オンラインサロンとは
〇過去の勉強会動画