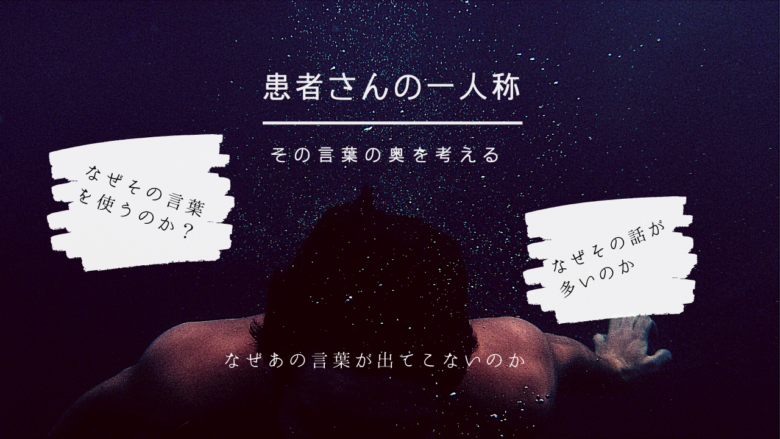お読みいただいている皆さんこんにちは!(こんばんは!)
本サロンを運営しております、理学療法士の唐沢彰太です。
今回は、リハビリテーションの臨床の中で欠かせないスキルの1つ、コミュニケーションスキルについて書いていきたいと思います。
リハビリにおけるコミュニケーションとは
リハビリが患者さん対療法士という構造を持っている以上、1対1でのコミュニケーションスキルが必要不可欠です。
またこれと同じくらい大切なのが、観察のスキルです。
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が一般の方と一線を画す能力でもあるこの観察スキルは、臨床そのものの質を変えてしまうくらい大切です。
ですが、一方で【外から見る観察】だけでは得られる情報には限界がある事を知っておかなければなりません。
例えば、どう動いているのか?は見れば分かりますが、なぜそう動いているか?は見ただけでは想像の域を越えません。
ここに、評価や検査を加えていくことで、観察で浮かんだ想像は仮説へと昇華していきますが、やはりまだ足りません。
では何が足りないのか?
患者さんの一人称です。
代表的なのは、感覚検査です。
感覚に関する答えは患者さんの中にしかありません。
そうなると、必然的に患者さんに<聞く>スタイルの評価になります。
もちろん観察から感覚に関することを仮説立てる方法もありますがそれはサロン限定で…。
感覚以外にも患者さんの一人称からは非常に多くの情報を得ることが出来ます。
その方法と情報を簡単に書いていきたいと思います。
コミュニケーションのポイント
患者さんの1人称を聞き出していく為には、最初に書いた通りコミュニケーションスキルが必要です。
- どんな質問をするのか?
- 質問で使う言葉は何が良いのか?
- 相槌のタイミングはどうするか?
- オープンな質問にするかクローズな質問にするか?
- 正面に座るか斜めに座るか?
- リハビリのどのタイミングで切り出すか?
- etc…
挙げればきりがありませんが、コミュニケーションには数えきれないほどの要因が関わっていることが分かるかと思います。
また、コミュニケーションにおいて特に重要になるのが、信頼関係です。
「この人(POST)には、この話をしても大丈夫」
「この人(POST)なら私の問題を解決してくれる」
などの、リハビリの専門家としての信頼を得ていなければなりません。
「話しても無駄」と1度でも思わせてしまうと、最も重要かもしれない内容を話していただけなる可能性があるので注意が必要です。
よって、基本となるのは
<傾聴>
<行動>
になります。
もしかしたら何気なく「ぽろっと」言った言葉が重要かもしれませんし、介入中に言った言葉が本心かもしれません。
介入中は少しも油断してはなりません。
患者さんの言葉をどうやっていかしていくか?
次に、患者さんが話した内容をどう考えて行くかです。
患者さんの言葉には、癖がある場合があります。
例えば、左側の股関節の運動覚の検査を背臥位(ベッドに上向きで寝ている状態)で実施している時に股関節を外転したとします。この時セラピストは、【外に開いた】と回答すると予測していたのに、患者さんは「左に動いた」と回答したとします。
ちょっとしたことですが、もしかしたら内側外側の概念よりも、左右の概念が認識しやすい可能性があるかもしれません。
そうなると、介入の時にセラピストの使用する言語は、内外より左右を使用したほうが患者さんはわかりやすくなってきます。
この様に、患者さんが使う言葉の頻度や介入している時の回答など様々な場面で情報が散りばめられています。
これを拾っていく為には、コミュニケーションスキルに加えて、観察・分析のスキルが必要になってくるのが分かるかと思います。
ですが、慣れるまでは意識していないと聞き逃してしまいがちですし、患者さんの一人称をどうリハビリにいかしていけば良いのかは、教えてもらう必要があると思います。
おわりに
近年痛みを有する方へのリハビリにおいて、患者さんの一人称が重要であることが認識されてきています。
私は、痛みを有する方だけではなく、リハビリを必要としている方すべての一人称が、リハビリの効果を向上させる情報だと信じています。
- 患者さんの一人称をリハビリに活かしていく方法に興味のある方
- コミュニケーションスキルから学びたい方
- 臨床に新しい切り口を作りたい方
ぜひオンラインサロンで一緒に勉強していきましょう!!
FAQもご参考ください。