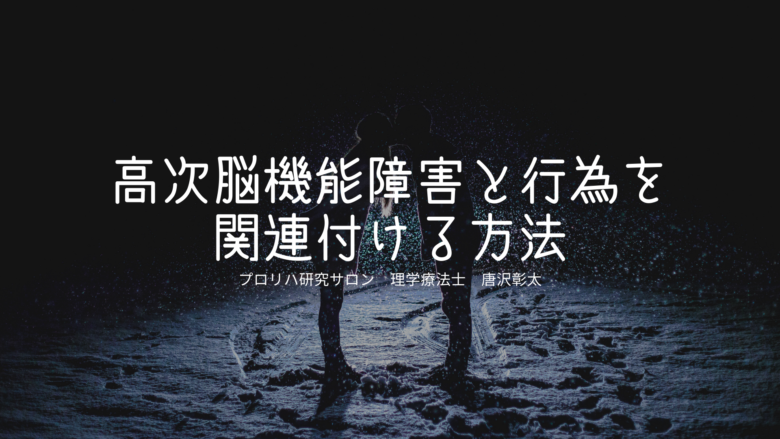お読みいただいている皆さんありがとうございます。プロリハ研究サロンの理学療法士、唐沢彰太です。(自己紹介はこちらから→唐沢彰太って誰?)
今回は、皆さんより多く声をいただいている高次脳機能障害について書いていきたいと思います。
その中でも特に、高次脳機能障害と動作をどう関連付けて行けば良いのか?に焦点を当てて行きたいと思います。
本テーマはトレンドでもあり、先日開催された日本神経理学療法士学会のカンファレンスでも取り上げられていました。
本学会では、半側空間無視と歩行についての関連性についての討論がされており、多くの療法士が悩んでいる現状を知るきっかけにもなりました。
実際、私の職場の療法士も、どうしても高次脳機能障害と動作を分けて考えてしまう人が多く、リハビリも悩んでいるという声を聞いています。
なぜこのような事態になってしまうのでしょうか?
高次脳機能障害を一言でいうと…?
そもそも高次脳機能障害の診断基準は日本ではどうなっているのでしょうか?
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部、国立障碍者リハビリセンターによると、
高次脳機能障害の定義
- 脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。
- 現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。(省略)
とされています。
つまり、高次脳機能障害は、
- 何かを認知することが出来ない
- 何かを認知しようとすると上手くいかず、エラーが生じる
- 認知できることに偏りがある
これらに加え、
- 認知した結果を動作に反映できない
- ある動作において必要な認知が出来ない
と考えることが出来ます。
リハビリの臨床において、高次脳機能障害を特定していく為には、検査が必要です。
検査結果から、ある高次脳機能障害が疑われれば、追加の検査を実施したりしながら病態の解釈へと進んでいくと思います。
それらを統合し、疑いがある〈高次脳機能障害へのアプローチ〉が開始されていきます。
もちろん正確に高次脳機能障害を理解するためには検査や評価は必須です。
それは言うまでもありません。
ですが、ここには大きな落とし穴が隠されています。それは…
- 検査を行わなかったものに関しては、見逃してしまう可能性がある
- 動作との関連性を考えることが非常に難しくなってしまう
この2点をクリアできなければ、本来の目的である生活の改善を目指すことが出来なくなってしまいます。
ではどうすれば良いのか?私なりの考えを書いていきます。
【情報】の落とし穴
リハビリでの介入は、情報収集から始まります。
年齢・性別などの基礎情報に加え、疾患名・障害部位・画像所見などの医学的情報、家族構成・家屋情報・職業などの社会的情報などを包括的に収集していきます。
その中でも、医学的情報の障害部位や画像所見は、介入前に情報を得ることで、患者さんの病態予測を行うことが出来ます。
そして、高次脳機能障害の検査の選択もある程度この時点で目星をつけていきます。
効率的かつ根拠をもって介入していく為には必要な手続きになりますし、必須であることは間違いありません。
ですが、先ほど書いた落とし穴の1番である、障害の見落としが発生する可能性は否定できません。
先入観の無い観察の大切さ
事前情報を最大限に生かしていく為には、【観察】が必要になります。
事前情報は予測する事を可能にしてくれますが、時には先入観となって観察内容に干渉してきてしまうことがあります。
錐体路が損傷していないから運動は問題ないだろうという考えが代表的でしょうか。
運動障害の原因は麻痺だけではありません。
補足運動野が損傷していたり、機能解離1)によって機能停止している場合では、運動を遂行できないケースも存在します。
私は、この様な事態を避けるために、観察と分析を分けて考えています。
- 観察:観察者の主観を入れずに、患者さんに生じている事象をそのまま記述する手続き
- 分析:事前情報、観察結果、検査結果などを統合し、病態を解釈していく手続き
この場合、先入観によって観察内容がズレることはありませんが、記述内容には工夫が必要です。
学生の頃に習った様な、「股関節が屈曲し…」の様な、関節運動学に基づいた観察だけではなく、むしろ患者さんの【振る舞い】そのものを記述していきます。
その中には、立ち上がりの時にはどこを見ていたか、何に気を付けていたのかなどの患者さんの1人称による発言も記述していく事も大切です。
この観察の中で気になった事、違和感程度のことでも構いません。それを記録として残しておき、検査の対象にしていきます。すると、検査の対象は、
- 事前に得た情報に基づいた検査(右の中大脳動脈の梗塞だから、半側空間無視の検査など)
- 観察や検査、評価を行っていて気付いたこと、違和感を解釈するために必要な検査(単関節では動きは良好なのに、歩行ではぎこちない:失行症の検査など)
と幅が広がっていきます。
高次脳機能障害と行為を結び付ける
ここまで書いてきた観察と分析を分けて考える方法は、障害の見落としが減るのはもちろんですが、もう1つ利点があります。
それは、
観察の中で気付いた点や動作の違和感であるため、動作と結びつけやすい
ことです。
「本患者さんには、半側空間無視がある」ではなく、
「歩行の時に麻痺側の振り出しがぶらぶらしているように見えるのは、全身動作において麻痺側に注意喚起が難しいからだ」
と、行為において生じている現象を理解するために、認知機能や注意機能の検査を行っていきます。
介入の一連の流れに、観察を取り入れ、検査の持つ意味合いを少し工夫すると、高次脳機能障害と行為とのつながりが見えやすくなるのではないでしょうか?
もちろん、この観察はすぐに出来るようになるわけではありません。
特に関節運動を中心に観察する方法を学校で習ってきた理学療法士は、観察の方法を工夫したり、時には1から組みなおす必要もあるかもしれません。
ですが、このような観察は訓練の幅そのものも広げてくれると考えています。
動作と高次脳機能障害の関係性が理解できていれば、訓練もおのずと認知的な側面(高次脳機能障害は認知障害であることを前提に)を考慮したものへと変化していきます。
つまり半側空間無視への介入、歩行への介入ではなく、
半側空間無視を呈している人への歩行改善を目的とした介入
です。
つまり、もっと歩きやすくなってもらう為には、患者さんを半側空間無視がある人として捉えて、訓練を工夫していくイメージです。
現在のリハビリでは、
- 歩行を改善していくためには、半側空間無視を改善していかなければならない
- 半側空間無視のあるなし関係なく歩行練習をおこなっていかなければならない
など、いろいろな考え方があります。
その中でも私は、高次脳機能障害を認知の癖として考えて、介入方法や関わり方、コミュニケーションまで全てをプランニングしていきます。
『こんな観察できるようになりたい!!』
『そんな訓練どうやってやるの??』
そう思っていただいた方、一緒に勉強してみませんか?
1)機能解離:限局性脳病変から離れて発生する神経生理学的変化を説明するために、1914年にvon Monakowによって提唱された概念。機能的に連結している部分などの脳血流量の減少や過剰興奮などが観察されている(E Carrera,et al 2014)
→脳損傷と機能解離(プロリハ研究サロンblog)
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
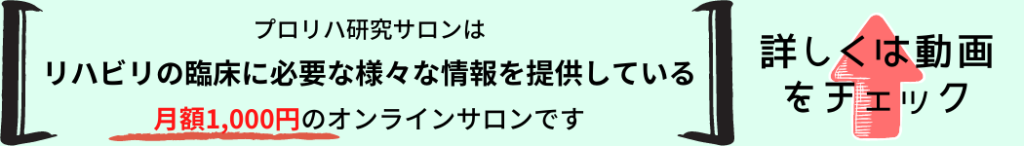
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
こちらもぜひご覧ください!!
〇過去の勉強会動画