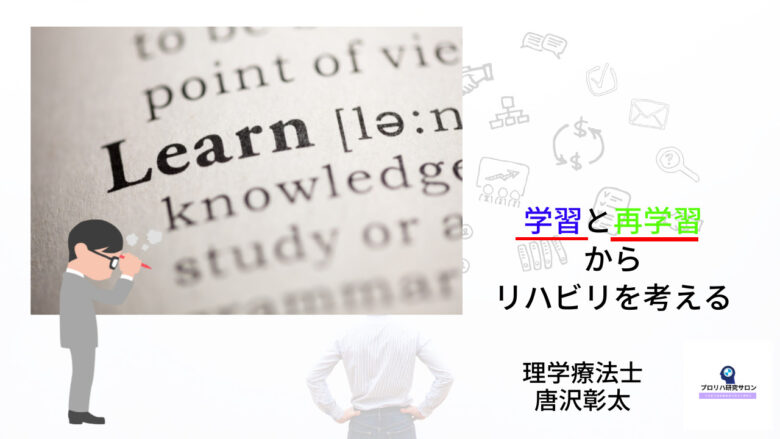お読みいただいている皆さんありがとうございます。プロリハ研究サロンを運営しています、理学療法士の唐沢彰太です。(自己紹介はこちらから→唐沢彰太って誰?)
行為の獲得が目標になるリハビリテーションにおいて、学習はかかせません。その学習ですが、リハビリではそのほとんどが【再学習】によって行われます。つまり、1度学習したことを再度学習することがほとんどです。
起き上がりや立ち上がりなどの基本動作は、脳卒中などを発症する前は無意識で行われていた動作です。これらの動作をもう1度出来るようにするのがリハビリの目的になってきます。
この様にリハビリは再学習であることを意識して介入することは大切なのでしょうか?今回はこの学習と再学習について書いていきます。
1度出来ていたことのメリットとデメリット
経験したことがないことが出来るようになる学習と、1度で来ていたことの再学習とでは何が違うのでしょうか?学習にはいくつかの理論があり、学習自体の方法も様々です。報酬を得るために、予測と結果にもとづいて洗練化していく過程をもつ学習は、今までの経験から様々な試行錯誤を行っていきます。
では、再学習はどうでしょうか?例えば立ち上がりを獲得したい時に、発症前の立ち上がりの記憶は役に立つのでしょうか?
答えはイエスです。脳が損傷し、運動や感覚が発症前と異なっているとは言え、身体の構造などは発症前と当然変わらず、立ち上がりに必要な手順などの大切なポイントは変わりません。
つまり、発症前にどうやって立ち上がっていたのかを参考に、今の脳でどうやったら立ち上がれるのかを考えることは、再学習においてとても大切になってきます。ですが、発症前と「同じように」立とうとすると、内反や反射などの異常な反応が出現してしまうため、今の脳で身体を認識出来ていることが重要です。
脳卒中における学習の落とし穴
先ほど書いた通り、学習にはいくつかの理論があります。これらを参考に、リハビリを組み立てていくことは非常に重要です。
ですが、ここで1つ重要なことが見落とされてしまうことが多々あります。それは…
【リハビリは病気を患ってしまった方を対象としていること】
どういうことでしょうか?つまり、学習理論がそのまま使用出来ない人が多くいるということです。
例えば、学習は今よりも効率よく出来るようになることが大切ですが、脳卒中などの疾患では効率よく出来るようになるではなく、動作をどんな方法でも出来るようになることが目的とされることがあります。
その代表例が分回し歩行です。股関節や膝関節が上手く動かせず、歩行の時に下肢を振り出せない時に骨盤から動かすことで振り出しを行おうとします。これは非常に効率が悪いはずですが、学習され定着していきます。
このように、効率面ではなく動作を何とかして行うことが目的となってしまうのです。このことに加え、脳に疾患をお持ちの方は、学習そのものが健常者とは異なる方法で行われる可能性があることを考えなければなりません。
- この患者さんはどうやって学習していくのだろう?
- 何が手掛かりなんだろう?
と考えて患者さんの解釈をしていくことが大切です。論文や知見をそのまま取り入れるだけではなく、患者さんのリハビリの参考にするという意識も大切です。
プロリハ研究サロンでは、
・実際にどうやって評価していくのか?
・その評価結果をどうやって介入にいかしていくのか?
臨床に直結する形で学べます!
こちらもぜひご覧ください!!
〇過去の勉強会動画