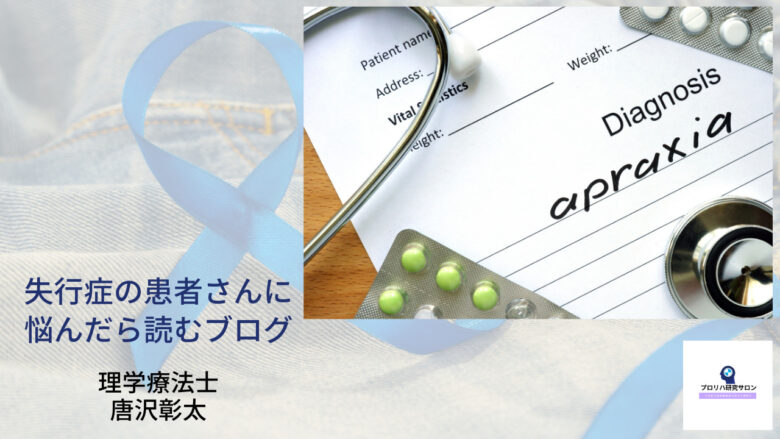お読みいただいている皆さんありがとうございます。
本サロンを運営しています、理学療法士の唐沢彰太です。
(自己紹介はこちらから→唐沢彰太って誰?)
脳卒中の後遺症を持つ患者さんのリハビリは悩むことが本当に多いです。
お読みいただいてる皆さんの中で、右半球損傷と左半球損傷とでどちらかに苦手意識をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
もし苦手意識がない方は非常に素晴らしいですし、お持ちの方も仕方がないことかと思います。
今回は、左半球損傷の患者さんのリハビリが苦手な方に失行症に焦点を当てて書いていきたいと思います。
左半球損傷=言語障害の先入観をなくそう!
右片麻痺の患者さんと言えば失語症が浮かぶのではないでしょうか?
失語症の影響でコミュニケーションがうまく取れない方のリハビリは確かに難しいです。
このような場合は、言語聴覚士がいるのであれば積極的に連携を取っていくのはもちろん、失語症でも全失語でなければコミュニケーションを取ることは十分に可能です。
まずは、コミュニケーションを取ることが出来た経験を積み重ねていってください。
別の視点で考えた場合では、言語障害の有無にかかわらず、動作や行為、生活を観察し分析していくプロセスは変わりません。
失語症に気を取られすぎず、いつも通りの介入をまずはしていきます。
その上で、言語を障害されていることによって動作にどの様な影響が出るのかも勉強していくと、さらにより良い介入が出来るようになってきます。
失行症と考えず、患者さんの特徴を捉えよう!
失語症とは別に、右片麻痺の患者さん左片麻痺の方と比べて様々な特徴があります。
例えば、
- 動きがぎこちない
- 関節の動きに動きすぎ、動かなさすぎなどの違和感がある
- 介入の効果が持続しない
- 動作の変化がなかなか見られない
- などなど
これらのほとんどに影響していることが多いのが、失行症です。
動作のスムーズさ、効率性、学習など様々なことに悪影響を及ぼし、リハビリの効果を低くしてしまいます。
ですが、よくある間違いとして上にあげたような特徴が見られた時に、失行症に関する検査を行って「この人は失行症だ!」と障害名を付けることが目的となってしまうことです。
このような手続きをすると、失行症に対するアプローチになり、
- 失行症について詳しくないとダメ
- 失行症に対する介入方法を知らないとダメ
となってしまいリハビリが進まなくなってしまうことが多いんです…。
高次脳機能障害を改善する!ではなく、高次脳機能障害をお持ちの患者さんの生活を変化する!と考えるべきですし、高次脳機能障害がどう行為に影響しているのか?を考えるべきです。
このことを考えると、失行症があるかどうかは検査するべきですが、患者さんの動きや認知面などの特徴をしっかりと捉えて、その特徴をベースに介入を考えていくことが重要です。もちろん失行症に詳しいことに越したことはありませんが、必要なことから勉強していくことも出来ます。
ぜひ意識してみてください!!
スペシャルセミナー行います!!
来る7/30に、
「パーキンソン病患者に対するリハビリテーションの考え方」というテーマでセミナーを開催します!
興味をお持ちの方はぜひこちらご覧ください!
→第3回スペシャルセミナー
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
こちらもぜひご覧ください!!
〇オンラインサロンとは
〇過去の勉強会動画