お読みいただいている皆さんありがとうございます。プロリハ研究サロンの理学療法士、唐沢彰太です。(自己紹介はこちらから→唐沢彰太って誰?運営者情報)
脳卒中後に見られる様々な現象の中でも、動作/行為を大きく阻害する1つが<内反>と呼ばれている現象です。内反は、足関節を母指側から背屈方向に動かす運動のことで、脳卒中後を中心とした疾患では、この足関節の運動である内反が意図せず出現してしまいます。
この内反は足底と床/地面との接地面を極端に減らし、時には足関節を捻挫してしまうこともあります。
すると、立ち上がりは非麻痺側での過努力性になり、立位ではバランスが低下します。さらに、歩行中は常に麻痺側の足首を気にして歩かなければならなくなります。
そこで、今回はこの内反に関する内容を書いていきたいと思います!!
内反と尖足
内反と合わせて良くみられる現象が<尖足>です。<内反尖足>といったように言われることが多いですが、明確に言うと内反と尖足は別々の現象です。
内反は既に書いた通り背屈方向の動きですが、尖足は底屈方向の動きです。本来反対方向の動きですが、内反尖足は底屈に回内が含まれている運動と考えた方が分かりやすいかもしれません。
つまり、小指側から底屈をする感じですね。
今回は、この尖足を伴わない内反に関して書いていきますのでご承知ください。
内反に、本人は「どうやって気付いているのか?」
さて、脳卒中の後遺症には、意図していない運動が出現してしまうものが非常に多くあります。
これは内反に限りませんが、これら意図していない運動が出現しないように動作/行為を行えるようになるためには、その現象に本人が気付けているかどうかが非常に重要になります。
そこで臨床では、患者さんに
「○○の時足が力んでしまいこうなってしまっている(内反している)ことに気付いていますか?」
と質問することがあります。この質問に対して、気付いていない場合は気付いてもらう手続きが必要なのですが、もし気付いていても注意が必要です。
例えば、リハビリの中で言われたことがある、家族がいつも注意してくるなど知識として内反していることを<知っている>ケースです。その他にも、目で見れば分かるなども知識として知っているケースと同様に注意が必要になります。
なぜでしょうか?
内反のような意図しない運動の出現が動作の中で見られている場合、その動作を行った時に出現しないような動作の獲得が必要になります。その時、自分がその動作をどうやって行っているのか?を体性感覚で知ることが重要になります。
もし、視覚で確認したり聴覚で得た知識でしか分からない場合は、常に目で確認しながら動作をしなければならないですし、誰かに指摘されなければ気付く事すら出来ません。
何より、内反が出ないように動くためには、体性感覚によって気付け、運動を自分で修正していける必要があります。
もちろん運動学習には模倣やコーチングなど、視覚や聴覚によるものもありますが、内反などの意図しない運動を改善していくためには体性感覚が重要なのです。
これらのことを考えると、介入を進めていく前に、患者さんが内反を体性感覚で感じられているかどうか、もし感じているならどんな感じがするのかを聞くことが大切です。
皆さんの患者さんは内反に気付けていますか?
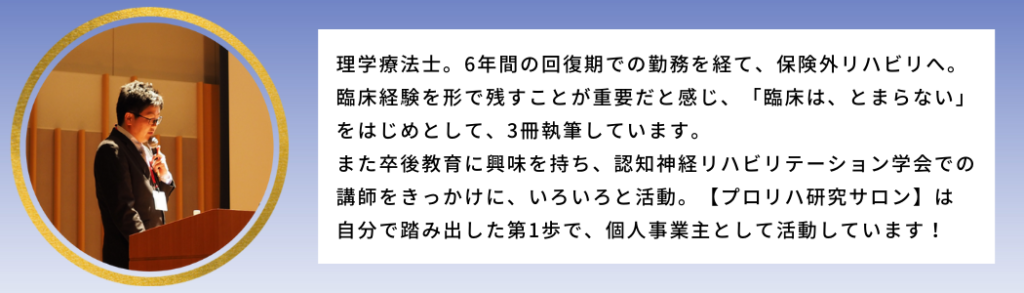
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
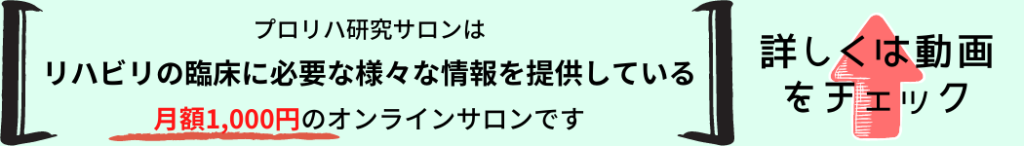
基礎から学びたい人から臨床を高めたい人まで
オンラインサロン会員募集中です!!
こちらもぜひご覧ください!!
〇過去の勉強会動画

